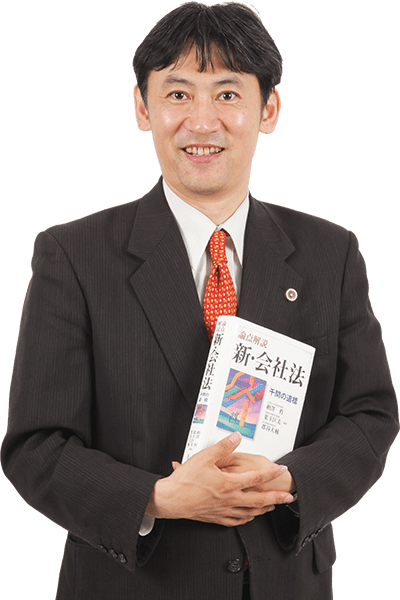Information
無料相談実施中!お気軽にご相談下さい。
24時間・時間外受付可能!
- 092-725-8777
受付時間:平日午前9時~午後5時30分 - ご相談・ご予約・お問合せ
単一の交通事故で、同じく訴えられた人の裁判への補助参加は許容される
- 更新日:2025.8.19
- 投稿日:2022.3.1

交差点で丙運転自動車と乙運転自動車が衝突し、その反動で丙運転自動車が、付近を歩行中の甲に衝突したため、甲が負傷しました。そこで、甲は、乙と丙を被告として、共同不法行為を理由とする、連帯しての全額賠償を求める訴訟を提起しました。
第1審は、交差点での衝突の際に、丙には過失ゼロだったとして、甲の丙に対する請求は全額棄却し、他方、甲の乙に対する請求を認容しました。甲の乙に対する請求認容については、乙からの控訴なく第1審判決が確定しました。
他方、乙は甲に対して賠償義務を履行したのちの、乙から丙に対する求償権行使に備えて、第1審判決直後に甲への補助参加を申し出て、かつ、甲と丙との間の請求棄却判決に対して、補助参加人として控訴を申し出ました。
この補助参加申出に対し、丙が異議申立をなしため、この事案で乙の甲への補助参加の利益を是認できるかが問題となったのが最高判1976/3/30判タ336号216頁です。
「補助参加の利益」とは?

補助参加を認容するためには、補助参加の利益が是認される必要があります。補助参加の利益の存否を判断する際には、論理上当該訴訟の訴訟物である権利関係の存否が、参加申出人の法律上の権利関係ないし地位に何らかの法律上の影響を及ぼす場合を指すと抽象的には言われているのですが、俗に判決理由中の認定判断についての利害関係は、単なる事実上のものにすぎず参加の利益を是認するものではないと扱われています(判タ338号66頁、井上治典教授の新判例評釈)。この俗説を適用すれば、乙の甲丙間の訴訟における参加の利益は否定されることになる。なぜなら、甲の丙に対する損害賠償請求権の存否によって、乙の丙に対する求償権が当然にあることになるとはかぎらず、甲が丙に敗訴すれば乙の丙に対する求償が困難になるという事情は単なる事実上の利害関係に過ぎないとも割り切れるからである。
最高裁判所の判断:補助参加の利益を肯定

ところが、上記最高判1976/3/30は、補助参加の利益を是認できるとしたうえで、丙にも幾ばくかの過失はあったという補助参加人乙の主張を認めて、丙に乙と同額の連帯責任ありと第1審の判断を覆した第2審判決を支持すると説示しました。
「もし丙に過失が認められるならば、乙と丙は交通事故で甲が被った損害を共同不法行為責任により連帯して賠償すべき関係になるので、そのときは、乙が甲に対して賠償した分のうち、丙の過失に応じた負担部分を丙に求償できることになる。そして、甲と丙の間の本件訴訟で甲が勝訴して丙にも甲に対する賠償責任があることが確定すれば、乙の丙に対する求償権の行使も容易になり、反対に、甲の敗訴に終わり丙に賠償責任のないことが確定すれば乙の丙に対する求償権の行使は困難ないし不可能になる。ということは、甲丙間の本件訴訟の結果は、乙が将来甲に損害を賠償した場合に、丙に対する求償権を乙が行使するにあたって法律上の影響を及ぼすものということができ、乙には参加の利益がある」
実務における補助参加
実務上、補助参加はわりと見受けられるのですが、厳密に参加の利益を吟味したうえで参加している事案は意外と少ないように思われます。ときには、利害関係がシビアに対立するので、独立当事者参加を利用すべき所を安易に補助参加を使っていることもあります。
参加の利益を検討している判例はレアなので、せっかくの機会として紹介してみました。
久留米市で交通事故のお困りごとを福岡の弁護士に無料相談
私が交通事故に強い理由
-

高い専門性
特に、重度後遺障害の案件ほど、それらの専門知識の組み合わせにより、弁護士次第で獲得できる賠償金額が大きく変わってきます。
-

豊富な実績
交通事故案件について私と同じ年数を重ねて同じ分量を取り扱ってきた弁護士は、余り(特に九州山口のほうには)いないのではないでしょうか。
-

責任持って対応
菅藤法律事務所では、私自身が責任をもって全ての交通事故案件を対応させていただいております。
-

日々情報更新中
論文集の数行の記載から裁判例を探り出して、自己の主張の根拠づけに利用したことは何度あるかわかりません。