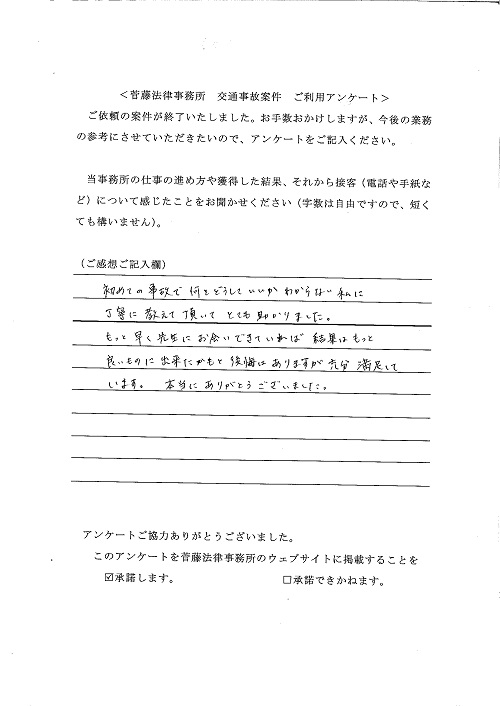Information
無料相談実施中!お気軽にご相談下さい。
24時間・時間外受付可能!
- 092-725-8777
受付時間:平日午前9時~午後5時30分 - ご相談・ご予約・お問合せ
廃用症候群による後遺障害を賠償対象とするためには
- 更新日:2025.9.30
- 投稿日:2025.9.27
第1、廃用症候群とは、身体を動かせない状態が続くことで、肉体的な機能の低下そして身体が動かせないことにより精神的な機能の低下が起こり、その結果として現れる症状の総称です。
廃用症候群の症状は多岐にわたり、肉体的な機能の低下では、筋力の低下・関節の拘縮・褥瘡(じょくそう。長時間同じ体位でいることによって、体重がかかる部分の血流が悪くなり、皮膚や皮下組織が破れたりうっ血すること)・尿路感染症そのほか誤嚥性肺炎(飲み込みが悪いため、誤って食道でなく気道のほうに飲食物や飲み物が入り込み肺炎をもよおすこと、死因に直結することも珍しくない)が挙げられ、精神的な機能の低下では、無気力になったり睡眠障害になったり認知症が進行したり状況が挙げられます。
医学論文は各自で探していただきたいですが(例えば園田茂氏著作の不動・廃用症候群という総括的な論文がネットで入手できます)、感覚的にも、高齢者の場合、ベッド上でずっと安静する状態が続くと筋力も気力も低下してしまうことは想像に難くないと思います。
第2、交通事故で入院生活を余儀なくされた被害者が、交通事故で骨折した部位以外の身体機能が低下した場面で、その骨折部位以外の身体機能の低下について廃用症候群の発症が交通事故と相当因果関係ありとして12級7号相当の後遺障害を認定した事案、京都地判2019年3月1日交民集52巻2号273頁を紹介します。
この京都地判の事案では、高齢の被害者は肝破裂・右副腎損傷・両側肺挫傷・右多発肋骨骨折・多発胸椎横突起骨折・右手指複数の腱断裂と骨折を被りました。自賠責は、受傷部位である右手指の機能障害と肝損傷に伴う胆のうの摘出の2か所を対象に併合9級認定しました。
訴訟の中で、高齢の被害者は、交通事故前は2階建の自宅でホームヘルパーの生活支援を受けながらADLが自立して一人暮らしだったのですが、長期入院によりベッドでの生活を余儀なくされることにより、肉体的機能が低下し、立位保持や歩行が困難になる廃用症候群に二次障害にさいなまれたからと、退院後は施設入居を余儀なくされたと施設費用の賠償を求めました。相手損保は受傷部位ではない二次被害なのだから廃用症候群の発症は交通事故と相当因果関係がないと反論しました。
第3、京都地判2019年3月1日交民集52巻2号273頁はこのように説示して、交通事故で直接受傷していない部位に廃用症候群を発症したことの相当因果関係を認めて、施設費用の賠償を認容しました。
1、高齢の被害者は、4カ月以上の入院治療を要し、そのうち5日間にわたり気管挿管され6日間にわたりICU集中治療室に入る必要があるほど、全身にわたり骨折するほど重症であった。
2、担当医は医療照会に’’両下肢機能低下の原因は、本件事故の受傷によって胸部及び腹部の損傷が著しく、長期臥床を余儀なくされたことによる廃用症候群である。高齢者の場合、長期臥床によって廃用症候群を生じることは一般に経験する事象である。被害者の両下肢機能障害と本件事故との間には医学的な因果関係があると判断する’’と回答している。
第4、このほか廃用症候群という疾病を交通事故に起因する後遺障害として認定した東京地判2005年2月24日交民集38巻1号275頁がありますが、こちらの東京地判の事案は交通事故により頭部に重篤な怪我を負い、後遺障害1級に該当する寝たきりとなった状況を廃用症候群と総称したものですので、むしろ相当因果関係が当然に認定されるべき状況にあると言えます。
第5、問題は、交通事故のあとに受傷部位の身体機能が用廃レベルに低下しても、交通事故により廃用症候群が起きたという因果関係を認定してもらえるのはむしろ例外ということです。
というのが、医療機関では受傷部位をほっておけば関節拘縮が発生すること明らかなので、悪循環を改善するためリハビリを実施するのが普通で、リハビリを継続することにより機能改善に資することが普通です。そのため、廃用症候群にり患したということは、そのリハビリを患者がさぼってしまっていたという患者側の事情に寄るために相当因果関係を認定しがたいという判断がおりがちなのです。
第6、わかりやすい例をあげると(あくまで仮定です私の経験例ではないです)、交通事故で膝脛骨を骨折しプレート固定をおこない1年後に抜釘したとします。抜釘までの間、リハビリを行っていたが、膝関節がすっかり拘縮してしまい、症状固定日時点では用廃レベルまで可動できなくなってしまっていたとします。
ところが自賠責は膝関節の機能障害について用廃を認定せずに、神経症状のみの認定にとどまることがあります。いざ画像所見を見てみると、膝脛骨のゆ合具合は関節面にやや不整はあるものの、関節がすっかり拘縮するほどの程度ではない、しかもカルテをさかのぼってみると、リハビリの途中では関節可動域がそれなりに回復していた、とうてい用廃という状況ではなかった。
とすると、膝関節の可動域が用廃レベルになってしまった理由は、リハビリを懸命に自宅で続けなかった患者の怠惰に起因するものとされ、そうなると交通事故と相当因果関係ある廃用症候群が膝に発生したとは評価できなくなるのです、あくまで被害者が招いた現状ということに。
そのほか、右脛骨高原骨折をおったのちに、認知機能が低下して寝たきりになったことの後遺障害補償を求めたものの、交通事故以前からの軽度認知症が進行しただけと廃用症候群と抗うつ事故との因果関係を否認した横浜地裁川崎支部2024年12月13日自保ジ2189号17頁もあります。
第7、このように考えると、上記京都地裁のように二次障害で廃用症候群を交通事故と相当因果関係あると認定するのは例外であり、被害者サイドとしてはその例外の立証にあたっては、リハビリを続けようにも無理な状況にあったなど担当医の協力を得てプラス廃用症候群の機序や発生確率に関する医学論文を付加して、交通事故との因果関係を具体的に立証していく作業が必要不可欠ということになります。