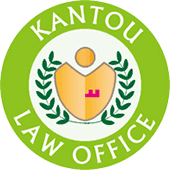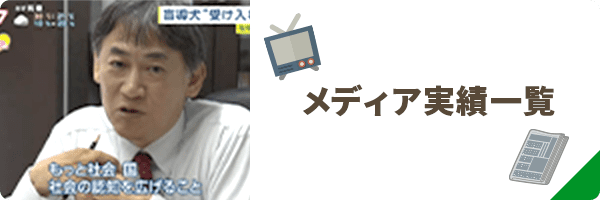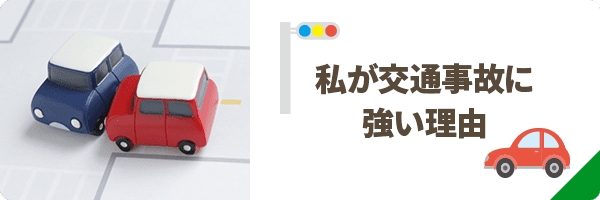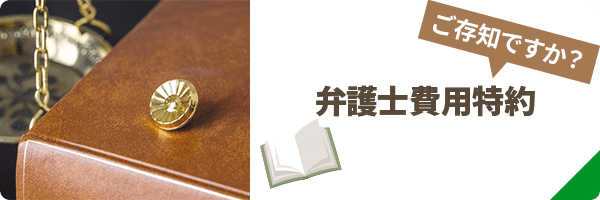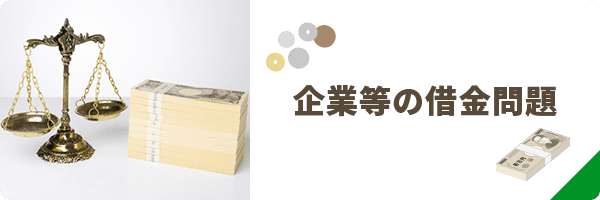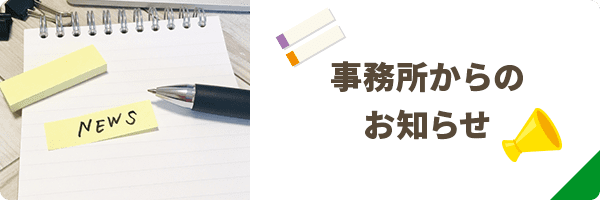私が交通事故に強い理由
無料相談実施中!お気軽にご相談下さい。
24時間・時間外受付可能!
- 092-725-8777
受付時間:平日午前9時~午後5時30分 - ご相談・ご予約・お問合せ

私が交通事故に強い理由
たくさんの弁護士が「交通事故に強い」「交通事故の取り扱いが豊富」とホームページや検索結果の宣伝文で告知しています。
しかし、その中でも真に「交通事故に強い弁護士がそこにいる!」と自他ともに評価できるサイトがどれだけあるのでしょうか。 これから、わたくしの特長をいくつかあげさせていただきます。
皆さん、「交通事故に強い」と名乗るに値するかをどうぞ確認してください。
REASON01交通事故被害は実は専門性が高い分野なのです
交通事故被害というのは、新聞に載らない日はないくらい、皆さんの日常生活の中でさほど縁遠い話ではありません。
ですけれども実は、医療・保険・労災や年金・自動車工学・物理学などに関する幅広くかつ高度な専門知識と、そして、経験を必要とする領域なのです。
特に、重度後遺障害の案件ほど、それらの専門知識の組み合わせにより、弁護士次第で獲得できる賠償金額が大きく変わってきます。
交通事故に重点を置かない一般の弁護士と比べますと、たくさんの裁判例を適切に抽出し自己の主張を説得的に繰り出していく能力などで経験の蓄積の濃淡がハッキリ現れますので、結果、必然的に取り扱い豊富な弁護士との間で大きな差が出てしまうのです。
依頼者がほかの弁護士が匙を投げた案件や能力に不安を感じ、私に再依頼された案件も多くありますし、ほかの弁護士から援助を求められたこともあります。
REASON02弁護士に就任して以来毎年数十件~百件近くの交通事故を解決してきました
私が弁護士になったのは1995(平成7)年ですが、それ以来、毎年欠かさず数十件~百件近の交通事故案件を解決してきましたし、現在もそれは変わりません。
その中で、過失相殺をめぐる激しい争いだけでなく、逸失利益の喪失期間や喪失程度をめぐり、精緻な主張・調査・証明が必要な案件を扱い続けて、経験を蓄積してきました。
医療でも料理の世界でも、研修を済ませ免許を取得した後、現場で様々な経験を経て(オンザジョブトレーニングと言われています)、ようやく一人前の仕事人になると言われています。
交通事故被害について弁護士が開設しているたくさんのサイトがありますが、交通事故案件について私と同じ年数を重ねて同じ分量を取り扱ってきた弁護士は、余り(特に九州山口のほうには)いないのではないでしょうか。
例えば、私がこれまで獲得した交通事故案件の判決は、交通事故案件を専門に取り扱う雑誌社からきわめて有用な内容と判断され、1度や2度にとどまらず、全国に向けて紹介されてきました(下の例は一例です)。
この事実こそ、交通事故案件のプロフェッションであることを雄弁に物語っているのではないでしょうか。
-
- 2004年6月30日
- 福岡地決(判時1960号103頁)
-
- 2007年3月2日
- 福岡地裁(交民集40巻2号359頁)
-
- 2009年9月30日
- 佐賀地裁(自保ジ1813号132頁)
-
- 2010年3月23日
- 佐世保簡裁(自保ジ1830号146頁)
-
- 2010年5月18日
- 福岡地裁(自保ジ1840号99頁)
-
- 2010年11月1日
- 福岡簡裁(自保ジ1842号150頁)
-
- 2012年3月30日
- 佐賀地裁武雄支部(自保ジ1877号134頁)
-
- 2012年9月13日
- 福岡高裁(自保ジ1882号22頁)
-
- 2012年9月28日
- 福岡地裁(自保ジ1888号1頁)
-
- 2013年10月10日
- 福岡高裁(自保ジ1911号26頁)
-
- 2013年12月3日
- 福岡高裁(自保ジ1916号24頁)
-
- 2014年10月23日
- 福岡地裁久留米支部(自保ジ1937号59頁)
-
- 2015年8月27日
- 福岡高裁(自保ジ1957号56頁)
-
- 2015年12月16日
- 福岡地裁小倉支部(自保ジ1981号90頁)
-
- 2016年4月25日
- 福岡地裁(自保ジ1980号20頁)
-
- 2018年1月18日
- 福岡高裁(自保ジ2027号77頁)
(今後も続きます)
REASON03わたしは別の弁護士に投げたりしません
弁護士が多数所属する事務所では、いったん依頼してみたものの、サイトに大きく掲載されている目当ての弁護士ではない別の弁護士とばかり打ち合わせて、サイトに大きく掲載されている目当ての弁護士とは一度も話したことが無かった(極端に言えば、契約書にサインをした時ですら、その目当ての弁護士とのやり取りは全く無かった)ということもあるそうです。
これでは依頼者にとって本当に責任ある対応をしてもらえるのか、不安になるでしょうし、すかされてしまった感じになるのではないでしょうか(特にその別の弁護士が弁護士になってからの期間がわずか数年の場合)。
菅藤法律事務所では、私自身が責任をもって全ての交通事故案件を対応させていただいております。
取り扱う交通事故被害の種類を限定させていただいているのも、被害者に一番優しい報酬基準を採用しながら、かつ、重度後遺障害・死亡事故のプロフェッションとして万全の仕事を行っていきたいとの考えからです。
REASON04たくさんの交通事故に関する文献を日々読んで勉強しています
交通事故が高度な専門知識を有することの表れとして、普通の弁護士なら日常的に使っている赤本・青本・別冊判例タイムズ(典型的な類型の事故の過失割合基準が示されています)のほか、自動車保険ジャーナル・交通事故民事裁判例集といった交通事故に特化した裁判例雑誌のほか、年1回発刊される賠償科学という医学の学会誌、その他たくさんの論文集があります。
その論文集の中には、いまや古本市場で数万円もする貴重なものもあります(わたくしもネットで見かけてビックリしました)が、わたくしは長年交通事故案件を解決してきたので、そういう本もシッカリ手元の蔵書に置いて、日々の交通事故案件において活用しています。
論文集の数行の記載から裁判例を探り出して、自己の主張の根拠づけに利用したことはそれこそ何度あるかわかりません。
また、定期的に有料で開催される医師による交通事故の講義を受けて、専門知識が陳腐化することのないよう励行しています。
さらに、交通事故案件に精通している整形外科医や整骨院とも、密な連携を築いています。どうぞご安心してご相談ご依頼ください。
このように、交通事故に関するたくさんの文献を日々読んだり、まさに日々自分を磨き続けることで、交通事故に重点を置かない一般の弁護士との、いざという場面におけるいかんともしがたい差につながり、それがプロフェッションの誇りある仕事に実るのではないかと痛感しています。