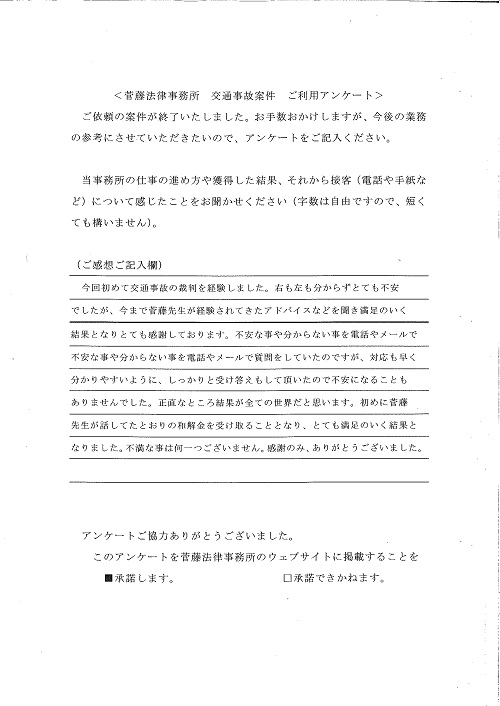Information
無料相談実施中!お気軽にご相談下さい。
24時間・時間外受付可能!
- 092-725-8777
受付時間:平日午前9時~午後5時30分 - ご相談・ご予約・お問合せ
弁護士に頼んでも損しない、費用倒れが避けられる場面は?
- 更新日:2023.9.30
- 投稿日:2023.9.30
Q:福岡県嘉麻市の横断歩道を歩行中、前方を全然見ていなかった自転車がぶつかってきました、怪我は骨折などない打ち身です。自転車は個人賠償責任保険に加入していたので、治療費は加害者が加入していた損害保険会社に支払ってもらい3か月通院して治療が終わりました。
相手損保から提示された金額がぜんぜん納得いかないので、こちらも弁護士を就けて対向しようと相談したのですが、相談した弁護士から「この件では弁護士に頼んだら費用倒れしますよ」と回答されました。
被害に遭ったのに弁護士に頼んだらかえって費用倒れが起きる場面と起きない場面の区分はどんな感じになるのですか?
なお加害者が自転車であり自動車やバイクでないので、自分の自動車保険につけている弁護士費用特約は適用ありませんと、自分が加入している保険会社からは伝えられています。
A:費用倒れとは、弁護士を就けても増額させる余地があまり見込めない事故のため、弁護士に頼んだときにかかる弁護士費用が、弁護士が介入することで増加予想される増幅額よりもより高くついてしまう現象を言います。このときは、経済的な面だけ言えば弁護士に依頼するメリットがないことになります。
例えば、相手損保からの提示された金額が30万円で、弁護士を就任されたときの料金が最低20万円だとしますと、弁護士が介入することで相手損保からの受取額が45万円にアップした場合であっても、依頼者の手元に残るお金は45万円マイナス20万円=25万円になります。 この場合、弁護士にはなから依頼しなければ30万円が手元に残ったのに、弁護士に依頼したことで賠償額がたとえ増加していても手元に残る額が25万円になってしまうので、経済的な面では弁護士に依頼するメリットがない、頼まないほうがむしろよかったということになるのです。
ですから弁護士に相談するときは、費用倒れにならないかどうかも、事前にその弁護士に確認しておく必要があります。この見通しを立てる上で、交通事故を多数扱っているかどうかは大事なのです。
菅藤法律事務所でも、相談時におうかがいした内容から、依頼しても費用倒れになるかどうかはきちんと説明させていただきます、費用倒れのおそれを払しょくできない状況でご依頼を引き受けることはありません、ご安心ください。
ちなみに、弁護士費用特約が利用できる場面では、自分の加入する保険会社が法律相談料は10万円・弁護士料金は最大300万円まで支払ってくれるので、その費用倒れをまねく心配を最初から取り除かれていますので、ぜひ普段から弁護士費用特約の適用範囲を広くする保険に加入しておくべきです。
最後に一般論ですが、交通事故で費用倒れになりやすいケースを類型化しました。いずれも弁護士費用特約が利用できないことを前提としていますので、弁護士費用特約が利用できる場合にはそれに当てはまらないです。
1つめは、冒頭に挙げたとおり、弁護士を就けても増額させる余地があまり見込めない事故のため、弁護士に頼んだときにかかる弁護士費用が、弁護士が介入することで増加予想される増幅額よりもより高くついてしまう場面です。Qのケースだと打ち身の通院のみ3か月で終了の事案だと、弁護士を就けないで相手損保から提示された金額のほうが、弁護士を就けて増額した金額から弁護士料金を控除したときの金額を上回ってることが多いです。
一般に、むち打ち症などの場合は、自賠責での後遺症認定を獲得できなければ費用倒れのリスクは払しょくできません。また、物損のみの事故でも費用倒れのリスクは高いです。
2つめは、加害者が賠償のための任意保険に加入していない場合です。自賠責保険を超える部分は加害者本人に請求するしかないのですが、任意保険にすら加入していない加害者が被害者の弁護士から直接請求されようとも、無い袖は振れぬとばかり賠償金が回収できないことが残念ながら珍しくありません。
3つめは、被害者の過失がそれなりに大きい場面です。被害者の過失が大きい場面では、弁護士を就けて項目ごとの金額が増加しても被害者の過失を乗じられることでその増加の効果が減殺されます(例えば、慰謝料の項目単価が100万円から150万円に50万円増額しても、被害者の過失が6割ならば、増加の効能は100万円×4割→150万円×4割と、実質は弁護士に頼んだときの効能は20万円の増額しかありません)。
被害者に少しでも過失があれば弁護士に依頼する効果がないというわけではないですが、被害者の過失割合を考慮しないまま賠償の見通しを立てると費用倒れになるかどうかの判断も誤ることになるので、交通事故に強い弁護士に相談することがこういう場面でも大事なのです。
4つめは、軽微衝撃を理由に加害者の付保する損害保険会社が受傷自体を否認している場面です。弁護士に頼んだときにかかる弁護士費用が、相手損保が受傷をみとめている場面よりも高額になることが多い半面、受傷を否認するくらいですから、相手損保から獲得できる金額もそう大きくは膨らまないことが見込まれるため、費用倒れのリスクが高いです。