Information
無料相談実施中!お気軽にご相談下さい。
24時間・時間外受付可能!
- 092-725-8777
受付時間:平日午前9時~午後5時30分 - ご相談・ご予約・お問合せ
福岡市南区40代夫婦(ともに14級)
- 更新日:2025.4.3
- 投稿日:2025.4.3
事故態様は、片側2車線道路の第2車線に渋滞停止中であった被害車両の左側面に、第1車線を走行していた加害車両が車線をはみだして衝突し、衝突後も加害車両はすぐに停止せず、被害車両の左側面を削りつつ突き抜けていったというものです。
事故当時、被害車両には、運転席に妻、助手席に夫、後部座席に幼児が乗車していましたが、さいわい幼児の症状がごく軽かったので、人身被害の中核は妻と夫の2名という状況でした。
交通事故に遭われてから時間を置かずに他の弁護士へ相談されたのですが、セカンドオピニオンということで当事務所にもご相談いただいたところ、私にぜひ依頼したいとご信頼いただきました。さいわい弁護士費用特約に加入されていましたので、弁護士費用の自己負担はありませんでした。まず症状がごく軽い幼児は事故から間を置かずに症状が消失し治療が終了したので、弁護士基準をもちいて短期間で示談解決しました。
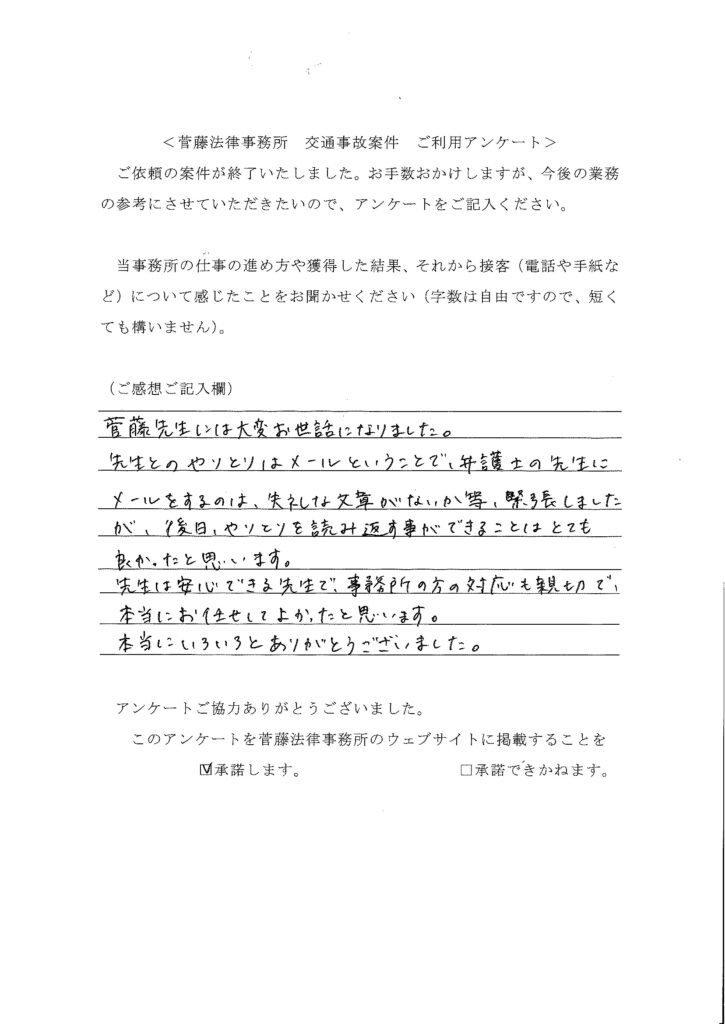
運転していた妻、助手席に同乗していた夫、2人とも骨折など画像所見をともなわないむち打ち症状をうったえ、当職からみても信頼を置ける整形外科医のところで、交通事故から間断なく十分な期間の治療を続けたのですが、お二人とも症状を消失させることかなわず、症状固定となりました。なお、治療途中で相手損保から治療費の一括対応を打ち切られましたが、主治医が積極的に症状固定がもう到来したと言っているわけではないのに、そこで治療を止めてしまうと症状が残存していても後遺症審査の際にはその止めた行動がマイナスと評価される危険があるので、主治医の了解の下、健康保険に切り替えて治療を継続することを選択しました。このような助言も、交通事故に強い弁護士をつけていたことでタイミングを逃さず、被害者夫婦は受けることができたといえます。
さて症状が残存してしまったのですから、お二人とも菅藤のこれまでの経験を活かして最大限後遺障害を認定してもらう確率をあげる医証そのほかの書類を用意した上で、万全を期して自賠責に後遺症申請したところ、想定とおり局部に神経症状を残すものとして14級9号の後遺障害等級認定を受けることができました。
後遺障害等級を受けたことで二人そろって相手損保に対し賠償請求を行ったところ、2人とも一括対応を停止した後の治療費をたとえ症状固定日前であっても全面支払拒絶したり、通院慰謝料や後遺症の部分の回答額も納得いく水準のものではなかったので、さらに妻については主婦休業損害の部分も納得のいく水準に到達していなかったので、やむなく提訴して裁判での決着を選択しました。
いざ訴訟に移行したら、相手損保がなんやかや減額するための主張してくることが提訴前から見込まれたため、お二人そろって提訴するよりむしろ、主婦休業損害の単価や休業割合という争点が入っていない夫のほうを先行して決着し、その解決後に妻のほうを提訴する時期をずらした二段構えで遂行する方針のほうが、時間は要するけれども当方は反論しやすくなるという戦術の合理性をご了解いただき、その手順で裁判をしました。
まず夫を原告とする裁判の中で、相手損保はなんと従前全く過失相殺を争っていなかったのに、被害車両は渋滞停止していなかった、第2車線で前進中途で起きた事故であるから被害者に過失相殺がなされるべきという主張を繰り出してきました。
しかし当方が衝突時まで渋滞停止していた事実は、刑事記録にも正確にその旨が記録されていることから、相手損保の主張こそ根拠もなく責任を軽減したいばかりに繰り出されていると反論し、加えて、たとえ第2車線上で被害車両が完全停止していなくても、本件事故態様は第2車線上の被害車両にとって全く回避の余地がなく、被害車両の過失相殺を基礎づける注意義務違反が見当たらないことを判例を用いて説得的に展開しました。
また、症状固定時期についても主治医の判断を尊重すべきということを、私の長きにわたる経験をもとに説得的に主張し、実際の休業はごく短期間で済んでも夫の労働能力が低下したり減収回避のための工夫を具体的に本人陳述書にて展開しました。
その結果、夫については、無事、過失割合を100:0をキープしたうえで、治療費についても相手損保の一括終了を越えて症状固定日まで認定してもらい、後遺症の損害なども満足のいく水準での和解勧告がなされたので、裁判前の相手損保からの支払回答額よりも十分増額するかたちで和解決着しました。なお、過失割合については、後日はじめる妻の裁判で相手損保がちゃぶ台返しをすることを見越して、しっかり加害者本人が100:0であることを認めることを和解調書に記載してもらいました(この危惧感に備えた対処が後日功を奏します)。
夫の裁判が終結した直後、妻についての裁判を開始しました。ところが、危惧感があたり、裁判官が夫のときとは別であるため、相手損保はまたもや被害者に過失があると主張を繰り出してきたのです。呆れましたが、夫のときの裁判結果も付け加えて、簡にして要を得る反論を展開しました。
さらに、補償対象とすべき期間や主婦休業の実態についても、陳述書にて医療記録の記載も用いながら反論していきました。同じ事故でも症状の軽重や怪我の治り具合(治療過程でカルテの中で医師が細かく記録しています)は個々それぞれ異なるため、夫と完全一致とはならなかったのですが、裁判前の相手損保の回答額よりも増額するかたちで和解勧告がなされ、妻についてもその水準で解決できました。




















