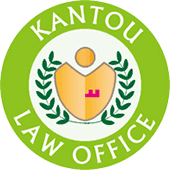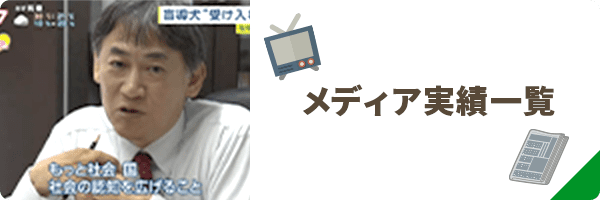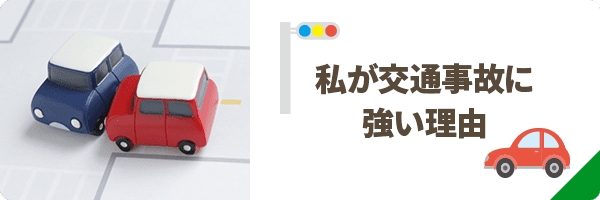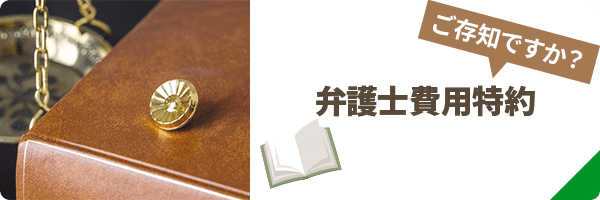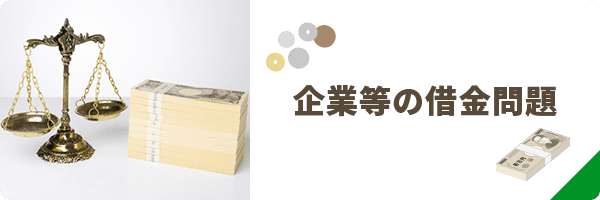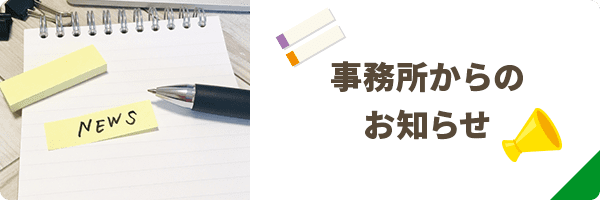Information
無料相談実施中!お気軽にご相談下さい。
24時間・時間外受付可能!
- 092-725-8777
受付時間:平日午前9時~午後5時30分 - ご相談・ご予約・お問合せ
糖尿病の合併症が交通事故後に悪化した場合の後遺症評価
- 更新日:2023.6.11
- 投稿日:2023.6.11
横断歩道を歩行中の62歳・役所の嘱託職員をしていたの被害男性が交差点を通過する加害車両に衝突され大けがを負いました。男性は、外傷性クモ膜下出血、多発肋骨骨折、肺挫傷など重傷を負い、遷延性意識障害に陥り事故の半年後に症状固定と認定されました。
ところで、被害男性は既往症で重度の糖尿病にり患しており、事故当時すでに片脚の指を切断していました。そして事故の1年後に糖尿病の悪化で両下肢を切断するに至り、事故の2年後には細菌性胸膜炎により死亡しました。
被害者の遺族は、症状固定時点以降の労働能力喪失率100%・就労可能年数について男子62歳の平均余命20年の半分である10年のさらに既往症の糖尿病を踏まえて半分の5年間と設定して、逸失利益を賠償請求しました。後遺症慰謝料として後遺障害1級に相当する分を請求しました。
これに対し加害者側は、被害者は交通事故の前から糖尿病のコントロールが悪く片脚の指を切断する14級に相当する後遺障害が存在していたことや事故後短期間での両下肢切断の事実を踏まえるなら、交通事故に遭遇せずとも遠からず両下肢をひざ関節以上で失い(1級5号)あるいは両下肢を足関節以上で失って(2級4号)、早晩糖尿病のために稼働できなくなっていたはずであるとして逸失利益の発生を否認し、かつ、後遺症慰謝料についても交通事故当時すでに糖尿病のコントロールが悪く14級に該当する後遺障害を負っておりさらに交通事故に遭遇せずとも重度の後遺症を抱える蓋然性が高度だったことから、全く疾患を抱えていない健常者が同じ状況になった場合と同一視するべきでなく減額されてしかるべきと反論してきました。
そして裁判所は、交通事故当時、被害者は役所の嘱託職員として普通に仕事に従事しており、そのときは糖尿病のコントロールとしてはインシュリンを用いていなかったことから、交通事故から1年半後に両下肢を切断する事態になったのは交通事故により長期間にわたって日常生活動作に全介助を要するほどの生活状態に置かれていたことが影響していると考えられ、交通事故に遭遇しなければ少なくとも短期間で糖尿病が悪化して労働能力を喪失することが見込まれる状況にあったとは認めらないとして、本件事故による遷延性意識障害を対象に労働能力喪失率を100%と認定しました。
同時に、裁判所は、しかしながら、交通事故時点で糖尿病にり患していたため、長期にわたる入院生活の影響があったとはいえ、交通事故から1年半後に糖尿病に起因して両下肢の切断手術を受けるに至っていることから、交通事故に遭遇しなくてもそう遠くない将来、就労が困難な状況に突入していた可能性が相当程度見受けられるとして、その点は、原告の主張に則し、労働能力喪失期間を男子62歳の平均余命20年の半分である10年からさらに半分の5年間に短縮することで調整するとしました。
また、後遺症慰謝料については、被害者が交通事故時点で14級相当の足指の切断という後遺障害を既に抱えていた点は、交通事故により負った遷延性意識障害という神経系統の障害とは系列も大きく異なるとして、1年半後に両下肢切断に至った点も含め、健常者が遷延性意識障害に陥ったに比べ、糖尿病にり患していることを理由にさらに減額することはしないとしました。
なお、交通事故から2年後に被害者は死亡していますが、死因は細菌性胸膜炎であり、交通事故に遭遇したこととの相当因果関係は認めがたいとして、逸失利益を算定する際の生活費控除はしないと認定されました。
この高松地判丸亀支部2018/12/19交民集51巻6号1493頁は、後遺症の損害評価の過程で、仮に交通事故に遭遇しなくても被害者の労働能力が糖尿病のため短期間で激減していたかもしれない特殊事情を、よく見受けられる素因減額に落とし込むのではなく(素因減額に落とし込まないことで健常者に比べての後遺症慰謝料の減額はない。糖尿病にり患していたから遷延性意識障害になったという関係がないから後遺症慰謝料を減額しないのは当然といえる)、交通事故に遭遇しなかったらいつから働けなくなっていたと推測するか(労働能力喪失期間の区切り)、交通事故に遭遇したことでその働けるであろう期間までの損害を幾らとみるか(認定対象となった期間の労働能力喪失率の評価)、このように論理的に思考形態がわかるようにスッキリ整理しており、同様の事案における損害構成方法として非常に参考になります。